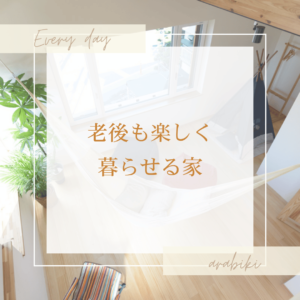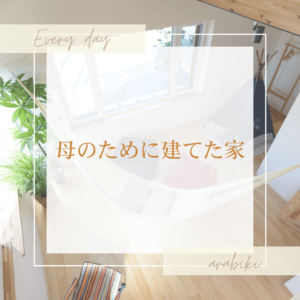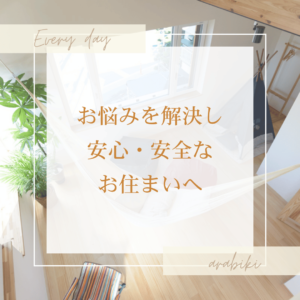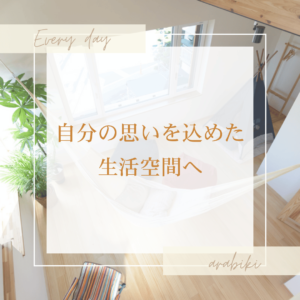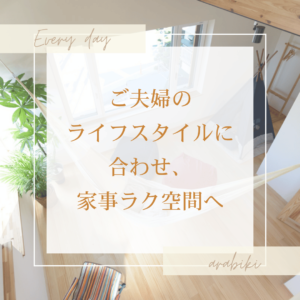母のために建てた富士見市の狭小住宅――小さな敷地でも叶える高性能・快適設計
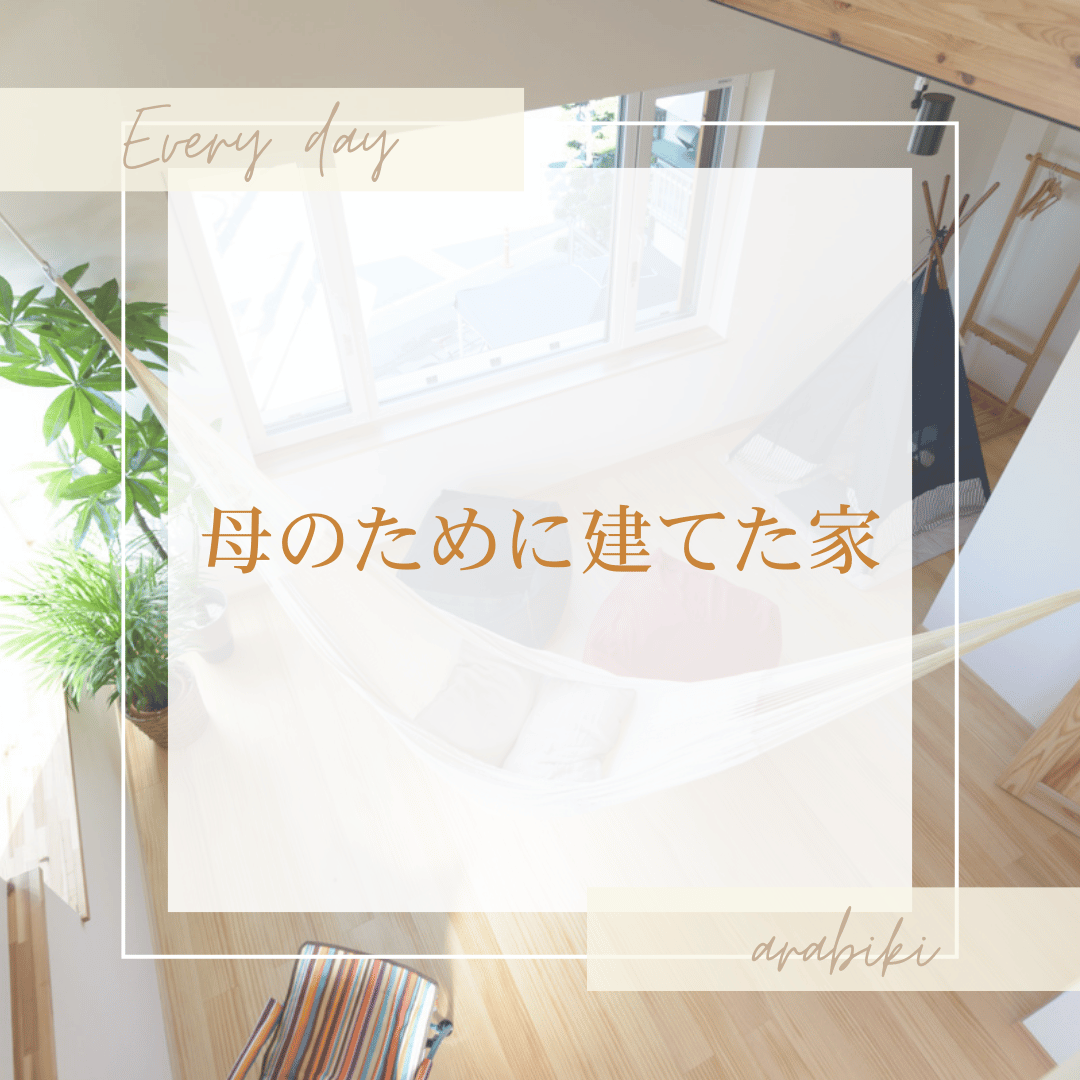




1. はじめに――「100年住み継ぐ」狭小住宅の魅力
息子さんがご年配のお母様のために建てた建坪約20坪の狭小住宅は、地域型住宅グリーン化事業の補助金を活用し、屋根には太陽光パネルを搭載したゼロエネルギー住宅です。「100年住み継ぐことができる家」をコンセプトに、高い断熱性能や高効率の設備機器を導入することで、省エネルギーと快適性を両立しています。小さな敷地でありながら、採光や通風、プライバシーに配慮した設計が特徴で、高齢の方にも安心な住まいとなっています。
狭小住宅というと窮屈なイメージを持たれがちですが、設計の工夫次第で広々と感じられる空間をつくることができます。この住まいは、“お母様がこれからもずっと快適に暮らせる家”という息子さんの温かい想いが形になった例といえるでしょう。
2. 地域型住宅グリーン化事業を活用した高性能住宅
この住宅では、地域型住宅グリーン化事業の補助金を活用したことによって、初期投資を抑えながら高性能な建物を実現しています。グリーン化事業の補助金を得るためには、一定の省エネ基準や耐久性、地域材の活用などが求められます。本住宅では、断熱性能を高めるために外壁や屋根、床下などの断熱材を充実させ、高気密サッシを採用し、熱損失を最小限に抑えるよう計画されました。
また、屋根に設置した太陽光パネルによって、日中は家庭内の電力をまかなうことができるため、光熱費の削減が期待できます。高齢者に配慮した住宅はバリアフリー設計だけでなく、ランニングコストの低減も重要なポイントです。限られた収入や年金で暮らす場合にも、負担を軽減できる省エネルギー住宅は大きな安心材料となります。
3. バリアフリーと将来を見据えた設計
お母様がより安全に暮らせるよう、可能な限りバリアフリーを意識したのが本住宅の大きな特徴です。玄関前には本来スロープを設置したいところですが、建物が道路に近いため、スロープを作ると急勾配になる可能性がありました。そこで、あえてゆるやかな階段とし、将来的に車椅子の利用が必要になった際には、後付けでスロープを設置できるような下地補強とスペース確保を行っています。
室内の動線についても、車椅子や歩行器などを使用する際に支障のない幅を確保し、扉のレバーハンドルや段差の少ない床仕上げを採用しています。さらに、廊下や洗面室の壁には手すりを取り付けるための下地が用意されており、年齢を重ねても安心・安全に生活できるように配慮されています。
4. 狭小住宅で空間を広く見せる工夫
限られた敷地のなかでも、より広々と感じられるようなプランニングが施されています。たとえばリビングの角にFIX窓(開閉しない窓)を配置し、視線を外へ抜くことで、室内に圧迫感を感じにくくなるよう工夫しました。FIX窓は外の景色を大きく取り込むことができるため、部屋の広さ以上の開放感を演出できます。
リビングから伸びる掃き出し窓はウッドデッキへ直接つながっており、ちょっとした屋外空間として活用できます。ウッドデッキに椅子やテーブルを置けば、自然光を浴びながら読書をしたり、家族や友人とお茶を楽しむことができるでしょう。狭い敷地であっても、こうした屋外空間を取り入れることで、暮らしの質を向上させることができます。
5. デッドスペースを活かした収納・生活動線
狭小住宅では収納不足になりがちなため、階段下や小屋裏など、いわゆる“デッドスペース”を有効に活用することが重要です。本住宅では、廊下を最小限にしながらも生活動線をスムーズにし、壁厚や床下を利用した収納スペースを確保することで、使い勝手を向上させています。特に玄関周りやキッチンの収納が充実すると、室内が散らかりにくくなるため、家全体をすっきりと保ちやすくなります。
また、メンテナンスが容易になるように、配管や配線をまとめて点検口を設けておくことも狭小住宅では大切なポイントです。限られたスペースだからこそ、修理や交換作業をスムーズに行えるような設計が求められます。将来的にリフォームを行う際にも、こうした配慮によってコストや作業時間の負担を軽減できます。
6. 耐久性を高める素材選びと構造
「100年住み継ぐ家」を実現するためには、耐久性の高い素材選びと構造計画が欠かせません。本住宅では、基礎部分や構造躯体に高い強度を持つ材を使い、地震や台風などの自然災害に備えています。また、壁体内結露を防ぐための通気層や、防湿シートの設置など、長期間にわたって家が劣化しにくいよう細部まで配慮されています。
さらに、高性能断熱材や遮熱性のある外壁材を組み合わせることで、夏は暑さを和らげ、冬は室内の暖かさを保ちやすくしています。こうした高断熱・高気密仕様の住宅は、ランニングコストを削減するだけでなく、室内の温度差を小さくすることでヒートショックなどのリスクを軽減し、高齢者にも優しい住まいとなるのです。
7. まとめ――想いをかたちにする狭小住宅
息子さんがお母様のために建てたこの狭小住宅には、「家族を想う気持ち」と「将来の変化に対応する工夫」がたくさん詰まっています。地域型住宅グリーン化事業を活用した高性能な設計、バリアフリーへの配慮、狭小地でも広々と感じられる空間づくりなど、限られた敷地を最大限に活かすノウハウが随所に盛り込まれています。
小さいからこそ、一人ひとりのライフスタイルや将来の変化に合わせて柔軟に設計を行うことが可能です。高い耐久性やメンテナンス性を意識すれば、長きにわたって家族の暮らしを支え続ける安心の住まいを実現できます。何より、「母のため」という温かい気持ちが反映された本住宅は、狭小住宅ならではの魅力と可能性を存分に示してくれる素敵な事例といえるでしょう。
家族を思う優しさと、限られた空間を最大限に生かすアイデアが融合したこの家づくりは、これから狭小住宅を計画する人にとって大いに参考になるはずです。“小さくても豊かに暮らす”というコンセプトを実践したこの住まいは、今後も家族の歴史とともに受け継がれていくことでしょう。
ー・-・-・-・-・-
一番ちかくの家守り
荒引工務店
代表 荒引登志雄
埼玉県富士見市水子3633-2
TEL:048-473-5333
ー・-・-・-・-・-